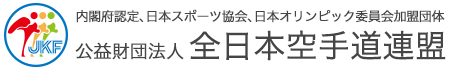コンテンツへスキップ
- 手技
- 立ち方
- 足技の部位と種類
- 受け技
- 礼法・精神・鍛練など
- 競技ルール
- 流派・形の名称
手技
- 正拳(せいけん)
- 相手の顔面や腹部、胸部への攻撃などで多く使われる拳。それだけにしっかりと拳を握るポイントは親指と小指にあり、拳の当たる部分は人差し指と中指の拳頭になります。手首と手の甲が直線になるように突く。突き技の基本です。
- 裏拳(うらけん)
- 正拳と同じ要領で握り、中指と人差し指の関節部を使用し、拳の甲側で相手の顔面や脇腹、胸部を攻撃する技になります。
- 掌底(しょうてい)
- 掌底とは、母指球と小指球の部位を指し、相手のアゴを攻撃したり、受けにも使われます。親指が掌の面もより前に出ない様に注意します。
- 鉄槌(てっつい)
- 正拳と同じ要領で握り、小指球の外側の部分で相手の頭部、顔面、腹部などを打つほか受けにも使われる部位または技です。
- 弧拳(こけん)
- 手首の付け根の部分で横から回し、相手の顔面、首、アゴなどを攻撃したりし、また受けにも使われます。
- 手刀(しゅとう)
- 親指を曲げて掌(てのひら)側に付け、親指以外の4本の指をそろえて伸ばし、小指球外側部分を固める。顔面や頭部の打ち技や当て技のほか受けや払いなどの防御にも広く使われます。
- 背刀(はいとう)
- 手刀の使用部位とは反対側となり、親指側の側面と中手指関節の近くを使う部位または技です。顔面や腹部などの攻撃のほか、受けや払いなどの防御にも広く使われます。
- 背手(はいしゅ)
- 手刀の甲側を使って相手の顔面や水月(みぞおち)、腹部などを攻撃する時に使い、また受けや払いなどの防御にも使われます。
- 貫手(ぬきて)
- 貫手は手の指をまっすぐ伸ばして指先で相手を突く技です。通常の突きよりも力を一点に集中させることが出来るため、みぞおち、脇腹、喉、目などの急所を攻撃する時に使います。
- 鉤突き(かぎつき)
- 正拳突き、下突きなどがまっすぐ突くのに対して、鉤突きは弧を描くようにして横から突き込む技になります。拳をねじりながらひじを外側に開き、目標に対して斜めから突くようにします。形のバッサイやジオンの中にも使われている技です。
- 猿臂(えんぴ)
- いわゆる肘(ひじ)を使った攻撃になります。「猿のように長い腕」という意味ですが、主に接近戦で相手の顔面(縦エンピ)や懐(横エンピ)を攻撃する肘技です。
- 順突き(じゅんつき)追突き(おいつき)
- 順突き(追い突き)は,踏み出した脚と同じ手で突く技です。腰から移動を始め,踏み込むと同時に突きを出すのが基本です。所定の位置に足がついた時点で身体の移動のスピードを止めて,その止めたことによって生じる力を腰の回転に転位させて突きのスピードに生かすというものです。
- 逆突き(ぎゃくつき)
- 「逆突き」は、空手における基本技の一つで、踏み出した脚とは逆の手で突く技です。足の回転の力を腰、上体、腕の順に伝えて踏み出した足と反対側の拳(正拳)で突きます。
- 刻突き(きざみつき)
- 「刻み突き」というのは、構えている状態から前足で踏み込みながら前拳で相手の上段を突く突き技です。後ろ足の引き寄せを素速く、その際頭の高さ(腰の高さとも)が上がらないようにするのがコツになります。
立ち方
- 結び立ち(むすびだち)
- 両足の踵が触れる程度に接し、つま先を約60度開いて自然に立ちます。
- 閉足立ち(へいそくだち)
- 結び立ちの姿勢のまま、両足を閉じた立ち方です。
- 平行立ち(へいこうだち)
- 両足の間は約30cm。両足の内側の線が平行になるように立ちます。
- 八字立ち(はちじだち)
- 平行立ちの足の位置から、つま先をやや外側に開いて立ちます。上半身はまっすぐに伸ばして自然体で立ち、目付は平眼。
- ナイファンチ立ち(ないふぁんちだち)
- 両足を左右、横一線に開き、両足のつま先はやや内向きにします。両膝をやや屈して内股を締め、さら両膝を軽くはります。重心は両足の中心に置き、足幅は60cm~65cmにします。(個人差あり)
- 四股立ち(しこだち)
- 足を左右に開き、その幅は約65cm。両膝を深く屈してつま先を外に開いて立ち、上体はまっすぐに伸ばし目付は平眼にします。
- 三戦立ち(さんちんだち)
- 流派によって若干の違いはあります。三戦立ちは基本の立ち方ですが、少し難易度の高い立ち方です。後ろ足のつま先と前足の踵を横一直線上に位置させ、後ろ足のつま先は真正面に、前足のつま先を斜め内側に向ける立ち方です。
- 基立ち(もとだち)
- 組手などで多く使われる立ち方。両足を前後に開き、後ろ足は正面を基準に約20度外に開き、前足は後ろ足と平行か、やや前向きにして立ち、両膝とも柔らかく曲げます。
- 前屈立ち(ぜんくつだち)
- 後ろ足の角度は基立ちと同じで、前足はまっすぐ向け、膝をしっかり曲げます。→膝が親指の真上ぐらい。後ろ足の膝は自然に伸ばして立ちます。
- 後屈立ち(こうくつだち)
- 後ろ足を真横に置く・後ろ足の踵の延長線上に、前足の側面が一直線上になるように立つ・後ろの膝しっかりと曲げて強く張る・前の膝はやや曲げる・重心=後ろ足:前足=7:3後ろの股関節部分を折り込む意識を持つと、引き締まった立ち方ができるようになります。また、後ろの膝が前を向かないように意識して張ると安定感がさらに増します。
- 猫足立ち(ねこあしだち)
- 後ろ足は約30度くらい開く・前足は正面を向け、つま先立ち・後ろの膝をしっかりと曲げ、腰を落とす・重心=後ろ足:前足=7:3でつま先より膝が前に出過ぎたり、後ろの膝が開きすぎたりしないように気をつけます。
- 騎馬立ち(きばだち)
- 平行立ちよりスタンスを広くする(腰幅の倍ぐらい)・膝が親指の少し内側になるぐらいしっかりと曲げる・十分に腰を落とす膝が内に入りすぎないようにしっかりと外に張るようにします。
- 横セイシャン立ち(よこせいしゃんだち)
- 前足踵の外側と、後ろ足先の位置は一直線上より少し離れ、両踵の距離はナイハンチ程度。
- 縦セイシャン立ち(たてせいしゃんだち)
- 前足先と後ろ足踵は、一直線上より少し離れ、両踵の距離は横セイシャン立ちと同じになります。 前足は正面に対し内側を向き、後ろ足先は正面に対して少し外側を向きます。
- 交差立ち(こうさだち)
- 主に形の中で登場する立ち方である。後ろ足の膝頭を、前足の膝裏に密着させ、足を交差する。その時前足を少し曲げる。体は正面に保ち、前足の踵と後ろ足のつま先を横一直線にする。
- 鷺足立ち(さぎあしだち)
- 流派によって若干の違いがあるが、片足で立ち、軸足でない足は太ももを水平にした状態で膝を曲げ、つま先を下に向ける。軸足と体の向きは正面に対して約45度に開く。
- 不動立ち(ふどうだち)
- 足幅は前屈立ちとほぼ同じにしてから前足を少し内に入れる。後ろ足の角度も前足と同じにする。両膝を十分に曲げ重心が中心になるようにする。
- 弁足立ち(べんそくだち)
- 正面に対して体を左に90度程度向け、左足の踵を正面に向け浮かせる。そのまま右足の膝裏を左足の膝に密着させ、両足の膝を少し曲げる。右足の踵と左足のつま先が正面に対して一直線になるようにする。
足技の部位と種類
- 爪先(つまさき)
- 足の指をそろえて、末節骨(まつせつこつ)を蹴りに使います。主に下腹部などを目標にして蹴ります。
- 足刀(そくとう)
- 足刀蹴りとは、足の側面の固い部分(足の小指側、第5中足骨、踵骨までの部分)で相手を蹴る技になります。喉、腹部、下段関節部を狙って使います。
- 背足(はいそく)
- 足の甲全体で蹴る時に使う部位です。相手の顔面や腹部などを目標に回し蹴りなどで使います。
- 踵(かかと)
- 踵部分を蹴りに使います。踵骨を使い、踵で踏み込んだり、後ろ蹴りで相手の腹部を目標にする時に使います。
- 膝(ひざ)
- 主に腹部蹴りへのなどに利用します。曲げた膝関節部で相手の水月(みぞおち)や腹部などの蹴りを極める時に使い、接近戦でその効果が大きいとされます。
- 前蹴り(まえげり)
- 蹴りの中で基本となる蹴りです。相手の前方に向かって行われる蹴り技で、途中膝を一旦たたみ、たたんだ膝を一気に開放して上足底で上段、中段、下段を蹴る技です。
- 回し蹴り(まわしげり)
- 回し蹴りとは、相手の上段や中段を弧を描くように横から蹴る蹴り技です。蹴りっぱなしでなく、引き足を取って技をコントロールすることが大切になります。
- 後ろ蹴り(うしろげり)
- 後ろ蹴りは、相手に正対した状態から後ろを向くように身体を旋回させつつ蹴りだした脚や踵で攻撃する技です。一時的に無防備な背中を相手に見せることにはなる上に、使用前と外した後に大きな隙を生じるが、回転のエネルギーが蹴りの威力に加算されるため、威力は大きいものがあります。
- 飛び蹴り(とびげり)
- 飛び蹴りとは、一旦跳躍してから蹴り技を放つ技です。飛び上がりながら蹴りを放つため、攻撃の速度や威力が高まります。相手の防御を突破する意外性や、遠距離からの攻撃に使われます。
受け技
- 上段揚げ受け(じょうだんあげうけ)
- 防御技の一つである上段揚げ受けは顔面に来る攻撃を下から上にはね上げた内腕で受ける技です。顔全体を覆うように受けを極めた瞬間は、拳が肘よりも高い位置に来ます。
- 中段外受け(ちゅうだんそとうけ)
- 防御技の一つである「中段外受け」は相手からの中段の攻撃に対して、腕を体の内側から外側に手首の回転を利用しながら受け流す方法です。ただし、流派や道場によって、この呼称が逆になることがあります。
- 中段内受け(ちゅうだんうちうけ)
- 防御技の一つである「中段内受け」は相手からの中段の攻撃に対して、腕を体の外側から内側に手首の回転を利用しながら受け流す方法です。ただし、流派や道場によって、この呼称が逆になることがあります。
- 下段払い受け(げだんはらいうけ)
- 防御技の一つである「下段払い受け」は、相手からの前蹴りなど概ね腰から下の「下段」への攻撃を効果的に受け流して対処するための防御技です。下段払いは多くある空手の型の中で、足の位置や立ち位置を変えながら、相手の多岐にわたる下段攻撃を想定して、最も多く出てくる防御スタイルの一つといえます。
- 手刀受け(しゅとううけ)
- 防御技の一つである「手刀受け」は相手からの上段から下段までの攻撃を手刀部で払うように受ける防護技です。受ける腕を内捻しながら、手刀で払うように受けを極めます。
礼法・精神・鍛練など
- 立礼(りつれい)
- 立礼は立ったまま行う礼で、試合開始や終了などの動作で行います。開足立ちで正面を見た姿勢から上体を約15~20度前へ傾けて礼をします。常に気を抜くことなく周りの雰囲気を感じながら礼をします。
- 坐礼(ざれい)
- 坐礼は正座の状態で行う礼です。座る時は左足からアクションを起こし、発つ時は右足から立ちます。礼をする時は左→右の順(もしくは両手一緒)に手を着き、両膝頭の前約10㎝の所に八の字形に置き上体をまっすぐに保ったまま礼をします。
- 残心(ざんしん)
- 武士道には「残心」という考え方があります。これは、戦闘が終わった後にも心を残し、隙を見せず精神を統一することを意味します。つまり「勝負が決してからの心のあり方」といえます。この考え方は空手や武道でも重要です。勝負の結果がどうであっても、礼儀作法を通じて、心を整え、常に油断せずにいることが求められます。
- 守・破・離(しゅ・は・り)
- 「守・破・離」とは武道の修行において修行者の成長と進化を段階的に表す哲学及び心構えです。「守・破・離」という言葉は、もともと千利休の訓をまとめた『利休道歌』に由来しています。「守」は修行者の基盤を築く過程です。修行者は師匠から教わった型や作法、基本的な知識を忠実に学びます。次に進むのは「破」の段階です。ここでは、修行者は経験と鍛練を通じて、指導者の教えを土台として、自分なりの工夫を加えます。最終的に、「離」の段階に到達すると、修行者は指導者のもとを離れ、独自の学びを発展させます。
- 空手道五条訓(からてどうごじょうくん)
- 人格完成に努ること 一、誠の道を守ること 一、努力の精神を養うこと 一、礼儀を重んずること 一、血気の勇を戒むること。空手の修行によって知性・教養を身につけるとともに体力を向上させ、どんな状況でも焦らず的確な判断と行動が取れるようにすることの教えになります。
- 空手に先手なし
- 本土に空手を普及させた船越義珍先生の空手二十ヶ条の二十番目に『空手に先手なし』という教えがあります。空手の技をみだりに使うことを禁じた戒めの言葉。武力というものは世の安定のため、人類の平和のためにあるのであって安易に行使してはならないという教えです。
- 道着(どうぎ)
- 空手を志す人の稽古や試合において必要不可欠な道着です。 もともと空手の創成期においては道着というものはなかったのですが、近代になって柔道着をヒントに作られたため見た目は似ていますが、空手着と柔道着には素材の厚みに違いがあります。
- 空手道憲章(からてどうけんしょう)
- 空手道のさらなる発展を期し、基本的な指針を掲げて「財団法人全日本空手道連盟」が定めた憲章で、空手道の修行を志す者は、空手道の品位と威厳を保つため、礼節、正義感、道徳心、克己、勇気からなる資質(倫理的規範)の涵養に努めなければならないという指針を表している。
- 段[位](だん[い])
- 段位とは、空手の技術・心得・精神的な成長を評価するために定められた格付けシステムです 。段位は初段から十段まであり、段位が上がるほど技術・心得・精神的な成長が求められます。空手を習う方は、段位昇進に向けて徐々にステップアップし、技術、心得、精神面で成長していくことが大切とされています。
- 巻藁(まきわら)
- 巻藁は古くから空手の稽古鍛練において使われる藁(わら)を巻いた鍛練道具で、肘から先、膝から先を鋼鉄のように鍛えます。 叩く、突く、蹴る部位を徹底的に鍛え強くする目的で使われます。
- 道場(どうじょう)
- 道場とは武道の稽古を行うための場所です。稽古場と呼ばれることもあります。
- 構え(かまえ)
- 空手において、構えは基本中の基本であり攻防の要となる重要な要素です。しっかりとした構えを身につけることで、技の威力を最大限に発揮し、相手からの攻撃を防ぐことができます。守りに強く、攻める時は素早く、姿勢を正しく保ち心を落ち着かせる。 これが構えの目的です。
- 運足(うんそく)
- 空手における運足(うんそく)は、自分の身体を正しく運ぶ(移動)ことです。組手でも形でも突きや蹴りや受けと上手に組み合わせることによってスムーズな技のキレにつながりますし、運足が正しくないとバランスの良い形や強い組手にならないほど大切な動作です。
- 転身(てんしん)
- 空手における転身(てんしん)は、自分のバランスを保ちながらすばやく身体の向きを変える動作のことです。転身しながらも重心を正しくばやく変えることも動作の大切なことです。
競技ルール
- 一本(いっぽん)
- 空手の競技の一つである組手競技、その判定ルールの一つです。全日本空手道連盟及び世界空手道連盟の競技規定での運用は、「上段への蹴り」・「足払い等の技で相手を倒した後の有効技」などで【1本】(3ポイント)になります。
- 技あり(わざあり)
- 空手の競技の一つである組手競技、その判定ルールの一つです。全日本空手道連盟及び世界空手道連盟の競技規定での運用は、「中段蹴り」、「背部への突き」、「それぞれの技が得点に値する複合の手技」、「相手を崩し得点した場合」などで【技あり】(2ポイント)になります。
- 有効(ゆうこう)
- 空手の競技の一つである組手競技、その判定ルールの一つです。全日本空手道連盟及び世界空手道連盟の競技規定での運用は、「中段突き」、「上段突き」、「打ち」などで【有効】(1ポイント)になります。
- 形(かた)
- 形は、仮想の敵に対する攻撃技と防御技を一連の流れとして組み合わせて決まった演武をする稽古形式で、「心」「技」「体」の鍛練を目的とした日本古来の稽古方法として確立されました。空手形の試合では、「いかに正しく演舞できているかどうか」「技の繰り出しができているかどうか」という2つの視点で審判から評価されます。
- 組手(くみて)
- 組手(くみて)は、主に二人で相対して行う空手の練習形式の一つ。 決まった手順にしたがって技を掛け合う「約束組手」、自由に技を掛け合う「自由組手」、勝敗を目的にした「組手試合」がある。
- 団体形・分解形
- 形競技には1人で演武する個人形競技、3人で呼吸を合わせて行う団体形競技があります。団体形では一通り形を打った(演武した)後に、その形の動きの意味を実際に演武する分解形があります。
- 先取(せんしゅ)
- 先取(センシュ)とは試合終了時にスコアが同じだった場合、最初のポイントを獲得したほうが勝者となるルールです。例えば、試合終了の時点で2−2で同点だとすると、一番最初にポイントを獲得した選手が先取となり勝者になります。
流派・形の名称
- 剛柔流(ごうじゅうりゅう)
- 日本本土における空手の四大流派の一つである剛柔流の流祖は、沖縄の宮城長順先生(1888-1953)であり、那覇手の大家である東恩納寛量先生から学んだ那覇手と、単身中国に渡って習得した拳法、双方の長所に独自の呼吸法「息吹」を加え、理論と実技を科学的に体系化し「剛柔流」と名付けました。
- 松濤館流(しょうとうかんりゅう)
- 日本本土における空手の四大流派の一つである松濤館流は、近代空手の祖とも言われる船越義珍を事実上の開祖とする空手流派である。船越義珍は、空手を本土に初めて紹介した人物として知られています。松涛館流は、遠い間合いからの一撃必殺を特徴とし、攻撃技・受け技などの動作がダイナミックであることが強みです。
- 糸東流(しとうりゅう)
- 日本本土における空手の四大流派の一つである糸東流は、摩文仁賢和によって創設されました。この流派の名前は、首里手を学んだ糸洲安恒の「糸」と、那覇手を学んだ東恩納寛量の「東」を取って名付けられました。糸東流はさまざまな武術を取り入れているため、突きや蹴りだけでなく、投げ技や逆技も含む総合的な格闘技術を有しています。
- 和道流(わどうりゅう)
- 日本本土における空手の四大流派の一つである和道流は、大塚博紀によって創設されました。松涛館流の空手技術を基に、柔術や剣術の技法を取り入れた独自の流派です。投げ技や足技など、柔術や柔道に似た技術が多く含まれており、空手の枠を超えた多様な技術体系を持っています。
- セーパイ(十八手)
- 全日本空手道連盟の第一指定型である「セーパイ」は剛柔流の形で、逆技・投げ技など接近戦での護身術として効果的な技が多く、特に巧妙な円の動きが特徴です。攻防技が一連になっていて緩急の動作をリズミカルにすることが求められる形です。
- サイファ(砕破)
- 全日本空手道連盟の第一指定型である「砕破(サイファ)」は剛柔流の型の中でも代表的な型である。外し技、打ち技が多く鷲足立ちで蹴るなどバランスを取ることが難しい剛柔流でも最も短く、異なる立ち方が多い形です。
- ジオン(慈恩 / 慈音)
- 全日本空手道連盟の松濤館流の第一指定型である「ジオン」は「慈恩」、「慈音」などと漢字表記され、首里手系の各流派に伝わる空手の型の一つです。おだやかな動きの中に激しい気魂のこもった形であり、転身、転回、寄り足などを体得するのに適している形です。
- カンクウダイ(観空大)
- 全日本空手道連盟の松濤館流の第一指定型である「カンクウダイ」は、首里手系の形で「クーシャンクー」または「公相君(コウソウクン)」と呼ぶ流派もある。この形は四方、八方に敵を仮想して各方面からのさまざまな攻撃を捌き、受けて反撃するもので非常に変化に富んだ形です。
- バッサイダイ(抜塞大)
- 全日本空手道連盟の糸東流の第一指定型である「バッサイダイ」は首里手の系統の形であり、基本技が集約され、攻防技の動作が連続的に組み合わされており、軽快な動きの中に、技の切り返し、強弱の使い方、敏速な極め技等の流れが求められる形です。
- セイエンチン
- 全日本空手道連盟の糸東流の第一指定型である「セイエンチン」は、那覇手の系統の形であり接近戦の技法が多く組み合わされ、蹴り技がなく、重圧な動きに特徴があります。演武線は左右対をなし、同一の動作が多く、呼吸と動作の緩急が一致している形です。
- セイシャン
- 全日本空手道連盟の和道流第一指定型である「セイシャン」は、首里手に属する和道流の形ですが、そんな中で一つだけ那覇手の流れを持つのがこのセイシャン(書物には那覇手の形であるセイサンに似ている部分があり、なんて考察もある)松濤館では半月(はんげつ)といいます。和道流セイシャンではセイシャン立ち、松濤館では半月立ちといいます。
- チントウ
- 全日本空手道連盟の和道流第一指定型である「チントウ」は、首里手に属する和道流の代表する形ですが、松濤館流では「岩鶴(ガンカク)」と呼ばれています。このチントウは、スピード感あふれる形ですが、片足(鷺足立ち)での連続技、二段蹴り、回って蹴り、などなど、とても難易度の高い形となっています。
- セーサン(十三手)
- 全日本空手道連盟の第二指定型である「セーサン」は、剛柔流の代表的な形の一つで、実戦的、護身的な技の体系と鍛練動作、剛と柔、静と動が巧みに調和されている形であり、豪快な突き、蹴りと素早いすり足、蛇のように相手の腕に巻きついての掴み技など変化に富んだ技が含まれています。
- クルルンファ(久留頓破)
- 全日本空手道連盟の第二指定型である「クルルンファ」は、剛柔流の形の中でも開掌を使用した攻防技が多い。また、動きの速い部分が多く、猫の攻撃の動きのように素早くそしてムチミ(ねばり)のある動きに変わる緩急の動作が特徴で静から動へのスムーズな変化が要求される形です。
- エンピ(燕飛)
- 全日本空手道連盟の第二指定型である「エンピ」は、身体の伸縮の多い形であり、いきなり身を沈めて突きと蹴りを受け、飛び込み反転しての敏速果敢な攻防の連続から最後は上段突きを左掌で受けると同時に、右手を相手の股間に差し入れて一回転しての肩車投げで終わります。さながら飛び舞う燕のような技の動きから、松涛館流では「燕飛」と命名しました。
- カンクウショウ(観空小)
- 全日本空手道連盟の第二指定型である「カンクウショウ」は、松涛館流の中で最も敏速果敢な形といわれ、棒の受けと反撃に特徴があります。 上段の棒受け、掴み捻って押し込む。さらに腔を払う棒攻撃に、膝をかい込み高く飛び上がり、一回転して反撃をかわす。最後も三日月蹴りから一回転して伏せて攻撃をかわし、鋭い中段突きで仕留めて終わります。
- マツムラローハイ(松村ローハイ)
- 全日本空手道連盟の第二指定型である「マツムラローハイ」は、糸東流の形で、鷺足立ちによる蹴りのさばき、開手による中段、下段の流し受け、相手の突きを巻き込んでの投げ技等に特徴があります。連続する技をダイナミック、かつ、スピーディーに演武することが要求される形です。
- ニーパイポ(二十八歩)
- 全日本空手道連盟の第二指定型である「ニーパイポ」は、糸東流の形で、中国拳法の流れを汲むものであり、身体の屈伸や円運動等による体捌き、受けからの肘固め、双手突き、一本拳の突き等の技法に特徴があります。これら攻防の技を敏捷に、また緩急の動作をリズミカルに演武することが要求されます。
- クーシャンクー
- 全日本空手道連盟の第二指定型である「クーシャンクー」は、首里手系で観空大、公相君等の名称で親しまれている形でもあります。和道流のこの形は真半身猫足立ち手刀受けが特徴といえます。形としては挙動数の多い方に属し、基本技が多く含まれ、特に上段への攻撃に対し体を低くし反撃に転ずるなど軽快で敏捷な形です。
- ニーセーシ
- 全日本空手道連盟の第二指定型である「ニーセーシ」は、和道流の形で、基立ち、四股立ち等のすり足で体の移動により技を極め、その場での立ち方の変化により攻防の技の変化を表し、流し技など軽妙な技法と回し受けも特徴です。
- 平安(へいあん)・ピンアン
- 「ピンアン」は、沖縄空手の型で、明治時代に糸洲安恒によって創作されました。この五段からなる型は首里手系の基本型として知られ、現在では首里手を含む多くの流派・会派で広く採用されています。
- ゲキサイ
- 剛柔流の流祖宮城長順によって初心者向けに創作されました。剛柔流の基本的および特徴的な立ち方と攻防の技が網羅されています。